2025年の活動報告と年末のご挨拶

日頃よりSDGインパクトジャパンの活動をご支援くださり、心より御礼申し上げます。 2025年は、多くのパートナーの皆さま、投資家の皆さま、そして日々対話を重ねてきた企業・関係機関の皆さまとの協働を通じて、弊社にとって数多くの挑戦と学びを積み重ねた一年となりました。 本年もSDGインパクトジャパンは、「サステナブルな社会の実現に向けて、イノベーションを促進し、新たな資本の流れを創る」というビジョンのもと、サステナビリティの促進と経済的な成長の両立を目指した事業創出や投資戦略に取り組んでまいりました。 気候変動や社会課題の解決を通じたサステナビリティの実現には、理念や個別施策だけでなく、「意思ある、色のついたお金」として、長期的かつ持続的に資金が流れ続ける仕組みをつくることが重要だと考えています。 その資本シフトの実装を目指して、弊社ではサステナビリティを軸に、インキュベーション事業とファンド事業に取り組んでおり、今年も各事業で具体的な活動を進めてまいりました。 脱炭素・カーボンクレジット事業 林野庁の森林由来JCMクレジットの調査事業に野村證券と共同採択 当社は野村證券株式会社とともに、二国間クレジット制度(JCM)を利用した植林プロジェクトの新規案件形成に向けたカンボジア国での現地調査を提案し、林野庁委託事業(令和7年度途上国森林プロジェクト連携推進事業)として採択されました。本調査では、野村證券と協働しながら、弊社のJCMクレジット創出に関する知見を活用して、カンボジアにおける森林分野のJCM案件形成を目指します。 インドネシア西ジャワ州でのバイオガス燃料転換を通じてGHG排出削減に貢献 当社は、環境省が実施する「令和6年度二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」に採択されました。インドネシアでは、家畜由来のメタン排出や化石燃料への依存が環境負荷の一因となっており、持続可能なエネルギー転換が喫緊の課題です。本事業は、インドネシア西ジャワ州において、家畜糞尿由来のバイオガスの生成設備を導入し、同国内の工場に供給することで、廃棄物の再利用によるエネルギー循環と、農業・畜産業の持続可能な発展の双方に寄与しながら、温室効果ガスの排出削減を実現するものです。 サステナブルテックインキュベーション事業 Ren Energy社との日本におけるジョイントベンチャー「Ren Japan」設立 当社は、サプライチェーンにおける企業向け再生可能エネルギー調達支援のリーディングカンパニーであるRen Energy社と、日本企業のグローバルなサプライチェーンと事業活動における再生可能エネルギー導入を加速することを目的に、新会社「Ren Japan株式会社」を設立いたしました。 Ren Energy社はこれまで、Nike、Target、Google、HPなど世界有数の企業に対してグローバルで包括的なサプライチェーンの再エネ調達支援サービスを提供し、スコープ2およびスコープ3排出量削減の取り組みを後押ししてきました。Ren Japanでは、このサービスを日本企業に対しても提供し、日本企業のグローバルな再エネ調達を支援してまいります。 RIMM Japanを活用する明治安田の「ESG評価サービス」がプラチナ大賞の奨励賞を受賞 RIMM Japan株式会社が提供するESG評価ツール*を活用した、明治安田の「ESG評価サービス」が、地方創生に資する優れた取り組みとして「第13回プラチナ大賞」において「奨励賞」を受賞しました。 *RIMM Japanの主力製品であるmyCSOは、サステナビリティ最高責任者が行うような、企業が抱えるあらゆるサステナビリティニーズに対応することを目的とした、アクセスしやすいエンドツーエンドのサステナビリティソリューションツールです。 サステナブルファンド事業 弊社の取組む上場株式エンゲージメント型インパクト投資戦略がBlueMarkの “Gold Rating” 獲得 当社が投資助言を行う上場株式エンゲージメント型インパクト投資戦略「NextGen ESG Japan」が、国際的なインパクト検証機関であるBlueMarkのFund Impact Diagnosticにおいて「Gold Rating」を取得しました。投資戦略、ガバナンス、マネジメント、レポーティングの4つの主要評価軸すべてで高評価を得ており、当戦略におけるインパクト・マネジメントおよびレポーティングの透明性と実践の質が高く評価されたものと受け止めています。今後も国際水準のインパクト・マネジメントおよびレポーティングの維持・高度化に向け、継続的に取り組んでまいります。 NextGen ESG Strategy Annual Report 2025 発行 本年も 「NextGen ESG戦略アニュアルレポート2025」 を発行し、投資先企業とのエンゲージメント活動の詳細や、インパクトの定量・定性分析や具体的な成果、それらの財務面への示唆などについて公開しました。多様な企業との継続的対話によって、ESG要素が企業戦略の中心に組み込まれつつあることも示されており、今後も投資先企業に対して積極的な関与を続け、財務面および持続可能性の両面でのインパクト創出を進めてまいります。 来年以降も、サステナビリティが理念にとどまることの無いよう、事業や投資を通じたイノベーションの社会実装や、サステナビリティの促進と経済的な成長を両立する意思ある資本の流れの拡充を目指してまいります。 引き続き、皆さまと共に新たな価値創出に挑戦していけることを、心より楽しみにしております。皆さまにとって、来る年がより実り多い一年となりますことを祈念するとともに、今後とも変わらぬご支援・ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 SDGインパクトジャパン一同 ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn
インドのクライメートテックVC(Sustainability Roundtable)オンライン・セミナーのご案内(11月26日 17:00~18:00)

第9回Sustainability Roundtable Sessionでは、インドのクライメートテックVCであるTheia Venturesが登壇いたします。 Theia Venturesは、エネルギートランジッション・ディープテック・脱炭素 にフォーカスし、インドを中心にプレシード〜シード期のスタートアップに投資を行っているVCです。 現在は、 英政府系開発金融機関 British International Investment(BII) をアンカー投資家とするファンドを通じて、重工業、製造業、マテリアル、モビリティなどの「hard-to-abate」セクターのサプライチェーンを含めた脱炭素に挑むスタートアップへの投資を進めています。 ファウンダーのPriya Shah氏は、米・英・インドで約17年にわたり、インパクト投資・クリーンテック・ソーシャルビジネスの最前線でキャリアを築いてきたクライメートテック投資のフロントランナーです。 Yunus Social Business(ノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス氏によるインパクトファンド)のインドファンドの立ち上げメンバーをはじめ、複数のインパクト投資機関やクライメート関連の財団・大学で、投資・助言・エコシステム構築に携わってきました。 サステナビリティ/インパクト投資に取り組む機関投資家・金融機関・事業会社の皆様にとって、下記の観点で、多くの示唆を得ていただける内容にしたいと考えております。 気候インパクトをどう投資判断に組み込むか インドの社会課題のソリューションとなるディープテック/ハードテック領域にどのようにアクセスをするか 成長市場インドでのクライメート・テック投資を、日本の事業/サプライチェーン戦略にどうつなげるか ご多忙とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。 お申し込みは下記のリンクからお願いいたします。 Theia Ventures オンラインセミナーのお申し込み *Sustainability Roundtable SessionはあかりキャピタルとSDG Impact Japanの共同で開催する、グローバルにサステナブルファイナンスに携わる実務家をお招きして、サステナビリティと投資に関する様々な議論を行う招待制サロンです。 【セミナー概要】 ■ 日時:2025年11月26日(水)17:00〜18:00(オンライン) ■ 言語:英語(Theia Venturesの説明は英語になります)/日本語 【主なプログラム】 インドにおけるインドの新エネルギー分野における市場環境 クライメートテックエコシステムと Theia Venturesの価値創造戦略 インドのクライメート・テック投資機会と日本との連携の可能性 投資事例・インパクトの捉え方 質疑応答・意見交換 【スピーカーのご紹介】 Priya Shah, Founder &Managing Partner 米英印で17年以上、ファイナンス、政策、ベンチャー分野に携わってきたクライメートテック投資の第一人者です。 インド有数の気候系起業家コミュニティ「Sustainability Mafia」のディレクターを務めるほか、大学やシンクタンク、アクセラレーター等でメンター・アドバイザーとして活動しています。 […]
2026年版EDCI報告の変更点とは?ESG指標・KPIの最新動向を解説
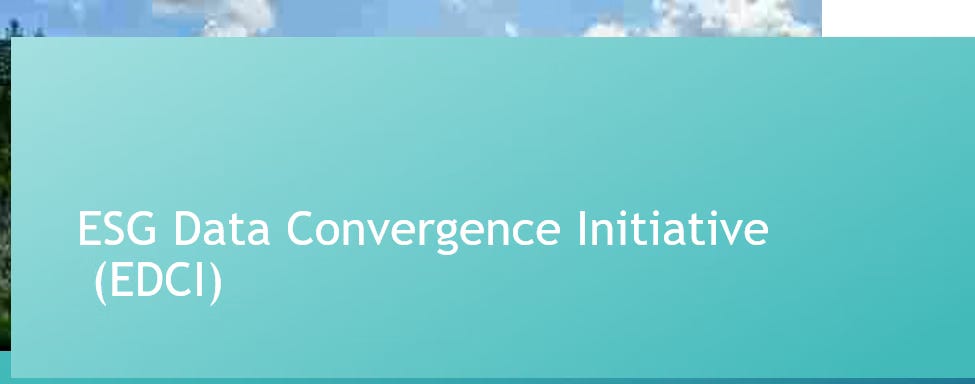
EDCIが2026年に向けてESG指標を改訂。サイバーセキュリティ指標の新設やScope 3排出量の重要性判断など、実務者必見の内容を解説。 2026年のEDCI(ESGデータ・コンバージェンス・イニシアチブ)の報告テンプレートにおいて、プライベートマーケット向けのESG測定指標がアップデートされました。本記事では、新たに導入された指標や既存指標への変更点、企業価値創出との関連など、実務に直結するポイントをわかりやすく整理します。 なぜ今回の変更が重要なのか? EDCIは、プライベートエクイティ市場におけるESGデータの標準化を目指す国際的な枠組みです。2026年に向けて行われた今回の「Metrics Sprint」では、153社のアンケートやフォーカスグループの意見をもとに、以下の重要な改訂が実施されました。 変更点のハイライト 1. 新指標の追加:サイバーセキュリティ 新たなKPIとして「サイバー脆弱性テスト」が導入 NIST(米国国立標準技術研究所)ガイドラインに準拠 オプション扱いながら、GP・LP双方で高い優先順位を持つテーマ 2. 既存指標の改訂 Scope 3排出量の重要性確認(Y/N):全体排出量の40%以上かどうかを問う欄を追加 短期目標のSBTi認証有無の明示:気候目標の信頼性向上 ファイナンスド・エミッションの精度向上:「アトリビューション・ファクター」の項目を新設(任意) 3. 価値創出との連動:商業成果タブの試験導入 ESG改善と企業価値向上の相関を測るため、「Commercial Outcomes」タブをパイロット導入 今後の重要テーマとして注目される分野 今後のポイント 提出率は全体で向上傾向(例:Scope 3排出量 42%→49%、従業員満足度スコアは初の30%提出)ですが、一部指標では引き続き提出率が低く、開示の拡充が求められる状況です(特に再エネ活用や従業員エンゲージメント)。 今後は、サイバーセキュリティやScope 3などの「ESGリスク」への先行対応が企業価値の差別化要因になります。また、SBTiなど外部認証の有無が信頼性のカギになるため、明示的な開示を意識すべきでしょう。さらに、ESG改善が企業価値につながるロジック構築(KPI→商業成果)に向けた準備も進めることが大切です。 まとめ 2026年のEDCI改訂は、単なる報告義務の強化にとどまらず、ESGと事業戦略の接続を促す大きな一歩です。各社のサステナ推進担当者は、今回の変更を踏まえた社内体制の見直しやデータ整備を早急に進める必要があります。 お問い合わせ 株式会社RIMM Japanhttps://www.rimm-japan.com/contact ※株式会社RIMM Japanは株式会社SDGインパクトジャパンの関連会社です。 ▼SIJの活動状況・ニュース 「NextGen ESG戦略アニュアルレポート2025」を発行しました SDGインパクトジャパンでは日本の上場株エンゲージメントインパクト戦略に投資助言を行っており、この度「NextGen ESG戦略アニュアルレポート2025」を発行いたしました。弊社では、投資先企業と密に連携し、ESG要素を企業活動の中心に据えるための深い対話と協働を通じて、企業の市場競争力を高めると同時に、持続可能な未来の構築にも寄与することを目指しています。 詳細はこちらから(弊社ウェブサイト) 「HARBOR Medical Innovation Challenge 2025@Science Tokyo」募集のお知らせ 弊社の関連会社であるBio Engineering Capital(BEC)は、医療系研究者・事業者・スタートアップを対象とした短期集中型アクセラレータープログラム「HARBOR Medical Innovation Challenge 2025@Science […]
Sustainability Roundtable Session(ウェビナー)のご案内(10月20日 17:00~18:00)

第8回 Sustainability Roundtable Session 第8回 Sustainability Roundtable Session では、欧州の独立系プライベート・エクイティ・グループ Argos (https://argos.fund/)が登壇します。 Argosは、35年以上にわたり、欧州のミッドマーケット(中規模企業)の潜在力を最大限に引き出す支援を行ってきた実績豊富な運用会社です。 同社のメイン戦略は、地域密着かつ横断的な支援体制を基盤に、ファイナンシャルレバレッジよりもオペレーショナルな価値創造を重視するアプローチを採用しています。経営変革や持続的成長を支えるハンズオン型の投資スタイルが特徴です。 直近では、従来のミッドマーケット投資戦略に加え、経済の根幹をなすサプライチェーンの脱炭素戦略を展開しています。この戦略では、既存ポートフォリオ企業の「グレイ(高炭素)からグリーン(低炭素)への転換」を支援し、産業構造全体の脱炭素化を推進しています。 欧州では、企業全体のCO₂換算排出量の約63%を中小企業(SMEs)が占めており、このセクターのトランジションは気候目標達成の鍵を握ります。Argosは、中小企業の変革を通じて、持続可能な未来と脱炭素社会の実現に貢献しています。 本セッションでは、脱炭素の取り組みがいかに企業価値の向上や持続的な成長につながるのかを具体的な事例を交えてご紹介します。投資家・事業会社の双方にとって、サステナビリティを成長戦略へと結びつけるためのヒントが得られる内容となります。 ご多忙とは存じますが、ご参加を心よりお待ちしております。 *Sustainability Roundtable SessionはあかりキャピタルとSDG Impact Japanの共同で開催する、グローバルにサステナブルファイナンスに携わる実務家をお招きして、サステナビリティと投資に関する様々な議論を行う招待制サロンです。 【セミナー概要】 日時:2025年10月20日(月)17:00〜18:00(オンライン) 言語:英語(Argosの説明は英語になります)/日本語 【主なプログラム】 欧州の中小企業の 「グレイ(高炭素)→グリーン(低炭素)」へのトランジションと価値創造の機会 経済的価値と環境的価値を両立させるために設計された独自のツールセットの紹介 投資先企業のケーススタディ 質疑応答・意見交換 【スピーカーのご紹介】 ■ ルイ・ゴドロン(Louis Godron) — マネージング・パートナー。プライベート・ エクイティ業界で35年以上の経験を持ち、そのうち33年間をArgos Fundで過ごす。元France Invest会長。欧州バイアウト市場のパイオニアの一人であり、現在はArgos Climate Action Fundに専念。 ■ ジャック・アズレイ(Jack Azoulay) — シニア・パートナー。フランス生態学移行省の元首席補佐官、フランス政府の国営企業を統括する株式保有庁の元ディレクター。現在はArgos Climate Action Fundに専念。 ■ アレクサンドル・レイシャー(Alexandre Raicher) — […]
ニュージーランド発の挑戦、OpenStar Technologiesが描く核融合の未来

先日、9月19日に開催されたOpenStar Technologiesのセミナーに参加しました。会場では、ニュージーランド発の若い核融合スタートアップが描く未来像に、参加者が熱心に耳を傾けていました。 世界ではいま、「夢のエネルギー」と呼ばれる核融合への期待が急速に高まっています。核融合とは、太陽が輝く原理と同じく、軽い原子同士を融合させて膨大なエネルギーを取り出す仕組みです。二酸化炭素を出さず、燃料も海水に豊富に含まれる水素から得られるため、もし実用化できれば地球のエネルギー問題を一気に解決できると考えられています。 これまで主役だったのは、フランスで建設が進む国際熱核融合実験炉(ITER)や、日本のJT-60SAといった巨大プロジェクト。ITERは総工費2兆円規模、JT-60SAも数千億円規模という国家級の取り組みです。一方で、民間の核融合スタートアップも急増しています。Fusion Industry Association(FIA) の報告によれば、2025年7月までの12か月間で、核融合関連企業は 26.4億ドル($2.64 billion) の資金調達を行ったとされています。また、対象となる 53 社の核融合企業の総調達額は 約 97.66 億ドル($9.766 billion) に達しており、2021 年以降で約 5 倍に成長していると記されています。「2040年代」ではなく「2030年前後の商用化」を目指す動きが世界中で広がっているのです。 OpenStar TechnologiesはSDGインパクトジャパンのパートナーVCであるIcehouse Venturesの投資先で、昨年12月にわずか設立から2年未満、そして投資額1,000万ドル(約16.9億円)未満で、核融合の最初のマイルストーンであるプラズマ生成(ファーストプラズマ)に成功したのです。これは従来、数千億円規模の国家プロジェクトが挑んできた領域であり、そのスピード感とコスト効率の高さは驚きを持って受け止められています。OpenStarは、主流のトカマク型やレーザー型ではなく、リバイテッド・ダイポール方式というユニークな方式に挑んでいます。これは、地球が磁場で太陽風を閉じ込めている仕組みをヒントにしたもので、中央に浮かせた超伝導コイルが磁場を形成し、プラズマ(超高温のガス)を安定的に閉じ込めるというものです。 実はこのリバイテッド・ダイポール方式のコンセプトは日本発祥なのです。物理学モデルは、1987年に故・長谷川晃教授によって提唱され、日本初のリバイテッド・ダイポール装置「RT-1」は東京大学院にて建設されました。さらにOpenStarは、2024年6月に京都フュージョンエンジニアリングと次世代核融合装置の実現に向けた協力関係を開始する覚書(MOU)を締結しました。 。 核融合業界はいま、数兆円規模の国際プロジェクトから数百億円規模のスタートアップまで、多様なプレイヤーが競い合う「群雄割拠」の時代にあります。OpenStarのように、日本発のコンセプトを引き継ぎ、ニュージーランドの開放的な政策の下で成長を目指す企業は、エネルギーの未来を描く新しい流れの象徴といえるでしょう。 ▼SIJの活動状況・ニュース ▽10月2日に当社Co-CEOの前川が、大阪関西万博で行われる「SDG’s beyond the future society for Life」に登壇いたします。弊社の事業の全体像や、インドネシアにおけるJCMの取り組みについてご紹介をする予定です。 会場:大阪関西万博インドネシアパビリオン日時:2025年10月2日 16:00-18:00 ▽当社CISO(最高投資戦略責任者)であるサシャ・べスリックが、「European Energy Independence through Investing in Renewables」に寄稿しました。本書では、欧州がEUと国家主権の基盤、経済的回復力、気候変動対策におけるリーダーシップとして、エネルギー自立をいかに緊急に追求しているかを掘り下げています。高まる地政学的緊張と加速する気候危機の中で、持続可能でエネルギー安全保障が確保された未来への道筋として、再生可能エネルギー投資への大胆な転換を提唱しています。 European Energy Independence through Investing in Renewables ▽当社CISO(最高投資戦略責任者)であるサシャ・べスリックが、8月28日と29日で開催された「Valuismカンファレンス2025」で「Circularity and Future Models for Value-Creating […]
TICAD9におけるアフリカ経済成長と脱炭素

8月20-22日に6年ぶりに横浜で開催された「第9回アフリカ開発会議(TICAD9)」は「TICAD9横浜宣言」の採択とともに8月22日に閉幕しました。この宣言ではインド太平洋とアフリカの連結強化による多角的貿易の実現、官民連携を含むアフリカへの投資、脱炭素の推進などが重要なテーマとして掲げられ、今後日本とアフリカが連携して取り組みが推進されていくことが期待されています。 当社がインキュベーションとして事業開発を進めている「脱炭素・カーボンクレジット事業」では、特に二国間(Joint Creditiong Mechanism: JCM)クレジットの創出を推進しています。この事業でもアフリカにおけるJCMクレジットの創出に取り組み始めています。 Thanks for reading SDG IMPACT JAPAN NEWSLETTER! Subscribe for free to receive new posts and support my work. その一つが、下記のセネガルにおいて省エネ型コールドチェーンの導入を推進するプロジェクトです。今年5月にUNIDO(国連工業機関)が実施する”UNIDO-JCM for Africa Program”において採択され、現在本格的に開発をスタートさせています。 国際連合工業開発機関(UNIDO)による二国間クレジット制度(JCM)を活用した「セネガル共和国ジャムナジョ(Diamniadio)の食品冷蔵施設における自然冷媒を使用した省エネ型冷蔵施設及び太陽光発電の導入」の採択について(環境省プレスリリース:https://www.env.go.jp/press/press_00122.html) 本プロジェクトは、セネガルの首都近郊において、屋根置きの太陽光発電を備えた省エネ型の冷蔵施設の建設を通じて、脱炭素を推進しながらコールドチェーンの強化を通じて、都市近郊により新鮮な生鮮品を供給するとともに、農産物などの廃棄を削減する取り組みになっています。 この事業は、北アフリカ地域でコールドチェーン事業を手掛けるIFRIA社とパートナーシップを組んで推進します。IFRIA社はすでにモロッコで省エネ型のコールドチェーン事業を展開しており、そのノウハウを活かしてセネガルへの展開を進めています。IFRIA社は国際的な気候変動基金であるGreen Climate Fundの資金で、脱炭素インパクトファンドを運営する米国のPegasus Capital Advisorsの出資先企業でもあり、本件はIFRIA社、Pegasus社、当社で連携して推進しています。 当社とIFRIA社との連携は、TICAD9の署名文書の一つとして取り上げられました。TICAD9における署名文書一覧(No.193に記載) また、石破総理をはじめとした日本・アフリカの首脳が出席する署名文書披露式典にも招待され、当社カーボンチームのソレン・プチコルが参加しました。TICAD9の署名文書は、TICAD8の92件を上回り過去最大の324件となり、その大半が民間企業によるもので、今後の人口増加、経済成長が見込まれるアフリカ市場への参入に対する企業の関心の高さが伺えます。 署名披露式典(当社は後方、写真左から3番目) アフリカの経済成長は今後ますます期待が高まると予想されます。経済成長とともにエネルギーやモビリティなどのCO2排出の増加も見込まれる中で、パリ協定の1.5度目標の達成に向けて、経済成長と脱炭素を同時に達成できる新技術を早期から導入していくことが求められます。このような新技術の導入には追加的なコストがかかるため、革新的なファイナンススキームの構築が肝要です。JCMは、このような脱炭素と経済成長を実現する新技術の導入に対するファイナンスの仕組みとしてアフリカにおいて、今後益々注目が高まると思われます。 ▼SIJの活動状況・ニュース SDGインパクトジャパンとRen Energy、日本法人「Ren Japan」を設立 当社とサプライチェーンにおける企業向け再生可能エネルギー調達支援のリーディングカンパニーであるRen Energy(以下「Ren」)は、日本企業のグローバルなサプライチェーンと事業活動における再生可能エネルギー導入を加速することを目的に、新会社「Ren Japan株式会社」を設立いたしました。 詳細は下記プレスリリースをご覧くださいhttps://sdgimpactjapan.com/jp/sdg-impact-japan-and-ren-energy-announce-joint-venture-ren-japan/ RIMM Japanのニュース 当社子会社の株式会社RIMM Japanは、企業のSSBJ(サステナビリティ基準委員会)基準への対応をワンストップで支援する「myCSOパッケージ」を本格始動いたしました。ESGマネジメント支援プラットフォーム「myCSO」の進化により、ギャップ分析からレポート作成、整合性評価まで、ESG初心者の方でも安心して取り組めるよう、段階的かつ確実に始められる支援をご用意しています。 詳細はRIMM Japanウェブサイトをご覧くださいhttps://www.rimm-japan.com/news/item/3c63a3b4-8c06-4677-8a99-e6a76defb5a6 ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link […]
企業の変革パートナーとして――NextGen ESG Japanの伴走型ESG投資

先日、法人のサステナビリティ情報を紹介するWEBメディア cokiでSDGインパクトジャパン(SIJ) の堀江 磨紀子と鈴木 早紀のインタビュー記事が掲載され、当社が投資助言を行っているNextGen ESG Japan戦略の特徴やアプローチについてご紹介しました。 ESG投資の“中身”が問われる昨今において、当戦略は、従来の枠組みを超えたアプローチを目指しています。一般的なESGファンドが既にESG評価の高い企業に注目する一方で、SIJの「NextGen ESG Japan」戦略は、“これからさらに改善する余地”をもつ企業に投資し、その変化をエンゲージメントを通じて引き出していくアプローチを取っています。 投資対象は、日本の株式市場に上場している中小型株です。企業との対話はIR部門にとどまらず、経営企画、人事、研究開発、マーケティングなど多様な部門にまで及びます。ファンド運用チームは、四半期ごとに企業を訪れ、課題を共有し、経営と現場の双方と深く向き合います。その対話は単なるヒアリングではなく、「問いかけ」から変化の種を引き出すプロセス。そしてその“変化の兆し”を、財務価値と社会的インパクトの両面で可視化する設計になっています。 NextGen ESG Japanは、SIJ独自の「Integrated Value Driver」フレームワークを中核に据え、ESG要素を単なるスクリーニング基準ではなく、企業価値創造のドライバーとして分析プロセスに組み込んでいます。エンゲージメントチームが一社一社に深く入り込み、数年にわたって企業価値向上に向けて財務とサステナビリティの観点で継続的な対話を行う体制を整えています。大変嬉しいことに、経営層からも「財務と非財務を統合的に見てくれる存在」として、高い信頼を得ています。 5月のニュースレターでもご紹介いたしましたが、このような取り組みが国際的にも認められ、2025年5月には第三者評価機関 BlueMark から “Gold”評価を獲得しました。アジアの上場株ファンドとしては初の事例で、戦略から運営・報告にいたるまで、国際的な基準に即した仕組みが整っていることが認められたかたちです。 NextGen ESG Japanは、単に「良い会社を見つける」のではなく、「良くなろうとする会社に伴走する」投資です。ESGが表層的なラベルではなく、企業文化や戦略に根差していくプロセスを、対話と分析、そして信頼を通じて丁寧に育てていく。こうした投資姿勢こそが、今後の日本企業に必要な外部パートナーシップのあり方を体現していると言えるでしょう。 財務リターンと社会的インパクト。その両輪を駆動させることで、持続可能な社会の実現に向けた「変化の連鎖」が今、日本の中小企業群でも始まっています。 詳細につきましては、cokiの記事をご覧ください。 https://coki.jp/sustainable/esg/55969/ ※コラムは、当社が関与する投資戦略に関する情報を含み、第三者メディアに掲載された記事の紹介・言及も行っておりますが、金融商品取引法に基づく広告または勧誘を目的としたものではありません。また、当該記事中に記載のあるファンド等に関しても、当社は特定の金融商品の販売や勧誘を意図しておりません。本記事の内容は投資判断の参考として一般的な情報を提供するものであり、投資の成果を保証するものではありません。投資に際しては、リスクや費用等を十分ご確認のうえ、ご自身の判断と責任により行っていただきますようお願いいたします。 ▼SIJの活動状況・ニュース 林野庁の森林由来JCMクレジットの調査事業に野村證券と共同採択 SDGインパクトジャパンはカンボジアの植林プロジェクトにおいて、野村證券株式会社(代表取締役社長:奥田健太郎、以下「野村證券」)と共同で、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)を活用に向けた調査事業が林野庁委託事業(令和7年度途上国森林プロジェクト連携推進事業)として採択されました。 詳細はPR Timesのプレスリリースをご覧くださいhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000091539.html RIMM Japanのニュース 当社子会社の株式会社RIMM Japanは、企業のSSBJ(サステナビリティ基準委員会)基準への対応をワンストップで支援する「myCSOパッケージ」を本格始動いたしました。ESGマネジメント支援プラットフォーム「myCSO」の進化により、ギャップ分析からレポート作成、整合性評価まで、ESG初心者の方でも安心して取り組めるよう、段階的かつ確実に始められる支援をご用意しています。 詳細はRIMM Japanウェブサイトをご覧くださいhttps://www.rimm-japan.com/news/item/3c63a3b4-8c06-4677-8a99-e6a76defb5a6 Bio Engineering Capitalのニュース 当社関連会社Bio Engineering Capital株式会社(BEC)社と、株式会社地域ヘルスケア連携基盤(CHCP)は、資本提携に関する契約を締結しました。本提携により、DX化を推進しているCHCPグループの医療現場と、BECの出資・支援先企業を有機的に繋げ、ヘルスケアスタートアップの有する技術の研究開発(R&D)や事業機会を創出していくことで、医療現場の効率化や新たなサービス提供に資するヘルスケアスタートアップの社会実装を加速させていきます。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000144993.html ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn
「可能性の世界」は静かに始まっている:企業、金融、社会の現場から見える転機

本コラムはCISOサシャ・べスリックのブログ「ESG on Sunday」(5月18日配信)を抄訳したものです。 「持続可能で公正な社会への移行は可能か?」その問いに対する答えは、イエスだ。しかし、それは即座に訪れる奇跡ではなく、時間とコストを伴う段階的な変化だ。にもかかわらず、いま確かに、その「可能性」は現実へと動き始めている。 欧州企業、気候政策を本気で支援 欧州では、企業が気候政策に対して本気で動き始めている。シンクタンクInfluenceMapによる最新の調査では、欧州主要企業200社のうち、気候目標と整合したロビー活動を行っている企業が2019年の3%から2025年には23%へと急増。一方で、気候対策に反対する企業は半減した。もはや「企業利益と気候行動は対立する」という前提は揺らいでいる。 注目すべきは、これらの企業が必ずしも大々的にアピールしていない点だ。むしろ、水面下で静かに政策を後押ししている。見出しを飾るのは否定派でも、実際に変化を起こしているのは、着実に動く実務派だ。 金融の構造改革はなぜ進まないのか 一方で、金融の世界では依然として持続可能性への本格的な対応が遅れている。ケンブリッジ大学の報告書は、気候変動や社会格差といった複合危機に対し、金融資本が十分に機能していない6つの理由を示した。 最大の障壁は「短期志向」。四半期利益を最優先する文化が根強く、気候リスクは長期的視点に立たないと可視化できない。また、規制の遅れや外部不経済(環境破壊など)が価格に反映されない市場構造も、金融の変革を妨げている。 にもかかわらず、世界の金融市場の規模は2023年末時点で1京ドル(1,000兆ドル)を超えており、そのうち株式市場だけでも115兆ドル。もしこれらの資本を気候技術、再エネインフラ、サステナブルな産業へと振り向けることができれば、巨大な変化を起こすことが可能となる。 再エネと電力網:インフラへの警鐘 再生可能エネルギーの導入が進む中で、新たな課題も顕在化している。最近スペインで起きた全国規模の停電は、再エネ比率の高まりによる周波数不安定が原因とされる。従来の火力発電が担っていた「慣性」(周波数安定化機能)が失われつつあるいま、電力安定の鍵は蓄電池とリアルタイム制御にある。 英国ではAI制御による巨大バッテリー(Blackhillock)がすでに稼働。プエルトリコやドイツでも分散型バッテリーが周波数維持に活用されている。再エネ普及と同時に、電力インフラの再設計が急務となっている。 リサイクル神話の崩壊と消費社会の限界 Circle Economyの最新レポートによれば、世界で年間消費される資源(1060億トン)のうち、リサイクル由来はわずか6.9%。2015年からさらに減少しており、改善どころか後退している現状が浮かび上がった。 問題の核心は、消費のスピードが回収・再利用の能力を上回っている点だ。しかも、多くの製品が実際にはリサイクル困難であり、理論上100%リサイクルできても、現実には最大25%が限界だという。つまり、「リサイクルすれば大丈夫」という楽観論はもはや通用しない。必要なのは、明確な「消費抑制」の方針と、製品設計段階からの循環型アプローチだ。 ESGと資本の逆風の中で 米国ではESG(環境・社会・ガバナンス)投資に対する政治的反発が高まり、多くの金融機関が姿勢を後退させている。その中でBarclaysは、「他が退く中で私たちは深く取り組んでいる」と発言。VWのグリーンボンド発行にも関与し、ESG市場の継続性を示している。 同時に、スイス再保険は「気候災害による保険損失は今年1450億ドルに達する可能性がある」と警告。金融機関が気候リスクを無視し続ければ、将来的な資産価格の急落(ディスオーダリー・リプライシング)の危険性が高まっている。 結論:可能性を現実に変えるのは誰か? いま、企業、金融、インフラ、消費行動のすべてが試されている。持続可能な社会は「可能」だが、それを「現実」にするには、構造の見直しと意思のある行動が必要だ。静かに、しかし確実に進み始めた「可能性の世界」を、私たちはどう受け止め、どう加速させていくのか。問われているのは未来への責任だ。 ▼SIJの活動状況・ニュース 当社のCo-CEO 前川と取締役 岡が、5/23に開催されたRaisina Tokyo 2025のパネルディスカッション“Weathering the Storm: Innovating and Adapting for Food and Water Security,”に登壇いたしました。 Linkedinhttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7335517650258694144 当社が出資しているBio Engineering Capital株式会社と株式会社地域ヘルスケア連携基盤と資本提携いたしました。 リリースはこちら ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn
NextGen ESG Japanファンドが、グローバルなインパクト投資検証機関 BlueMark社より「GOLD評価」を獲得
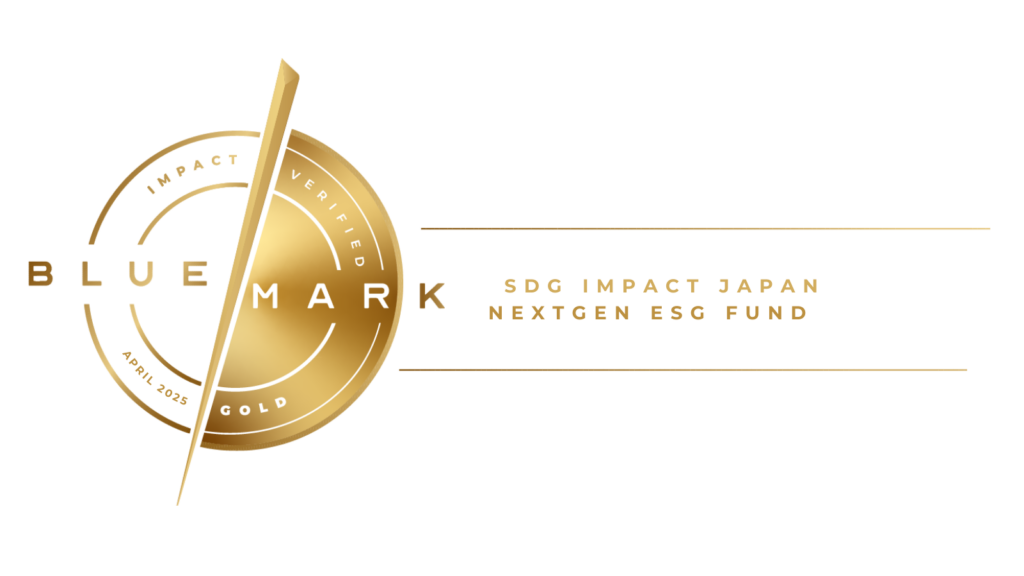
SDGインパクトジャパンが投資助言を担う上場株インパクトエンゲージメントファンド「NextGen ESG Japanファンド」が、グローバルなインパクト検証機関 BlueMark社より「GOLD評価」を獲得いたしました。 BlueMark社は、インパクト測定・マネジメントについてグローバルな業界標準に基づく評価・検証サービスを提供するグローバルリーディングカンパニーです。同社はFund Impact Diagnostic (以下、Fund ID)と呼ばれる独自の評価フレームを用いて、ファンドのインパクト投資実践状況を「Impact Strategy (インパクト投資戦略)」・「Impact Governance (インパクト投資実践のガバナンス)」・「Impact Management (インパクトマネジメント)」・「Impact Reporting (インパクトレポーティング)」の4観点・全44評価項目で審査・評価します。 今回のBlueMark社の評価結果では、NextGen ESG Japanファンドは上述の4観点の全てで「High」以上の評価を取得するとともに、Impact Reportingについては最高評価となる「Advanced」を取得し、全体では「GOLD」の評価となりました。 NextGen ESG Japanファンドは2022年4月に設定され、SDGインパクトジャパンがあすかコーポレイトアドバイザリーとともに共同で投資助言を行っています。同ファンドのポートフォリオは国内上場企業で構成されており、各社ともサステナビリティへの取り組みを自社の事業成長や競争力の源泉として積極的に位置づけ、その実践に強い関心を寄せています。私たちは、ポートフォリオ企業1社1社に対して、中長期の戦略を踏まえた戦略的なサステナビリティ課題を特定し、深い対話を通じてサステナビリティの取り組みを促進することで、持続可能性と競争力のあるリターンの両立に注力しています。また、投資家に対しても、インパクトの状況を含む詳細かつ透明性の高いレポーティングを実践してまいりました。 日本を含めグローバルでまだ実践事例の少ない上場株投資でのインパクトファンドとして、今回の評価で明確になった良点と課題の両方をしっかりと踏まえて、更なる取り組みの強化を進めて参ります。 ▼イベント・セミナーのお知らせ 「Weathering the Storm: Innovating and Adapting for Food and Water Security」に登壇いたします 5月23日に、当社Co-CEOの前川とManaging Partnerの岡が、JBIC/経済同友会/ORF共催のRaisina Tokyo 2025のパネルディスカッション「Weathering the Storm: Innovating and Adapting for Food and Water Security」に登壇いたします。当パネルでは、気候変動への懸念を背景とした、インド太平洋地域の各国における食料と水の安全保障の課題について議論する予定です。 ▼SIJの活動状況・ニュース 5/8に当社Co-CEOの小木曽がSusHi Tech Tokyo 2025のパネルディスカッション「エコシステムに今DEIが求められる理由~グローバルな視点・事例から見えるもの~」に登壇いたしました。 […]
EUが「オムニバス法案パッケージ」で規制簡素化を発表:EUのサステイナビリティ目標と政策は後退するのか?

今月のニュースレターでは欧州委員会が2月26日に公表した、規制簡素化のためのオムニバス法案パッケージを解説します。 オムニバス法案パッケージにおいて欧州委員会は、産業界の競争力とイノベーション力向上、投資機会と雇用の創出を目的として、企業サステイナビリティ報告指令(CSRD)[1]、企業サステイナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)[2]、EUタクソノミー規則[3]、炭素国境調整メカニズム(CBAM)[4]、といった、サステイナビリティな社会を実現する金融政策上の要となる広範な範囲の法律を改正し、規制を簡素化することを提案しました。 これらは一定の条件を満たす日本企業にとっても影響が大きい法律であり、2022年以降に適用開始、又は現在も移行期間にあるかなり新しい法律であるため、EUの状況を注視している読者も多いでしょう。規制によっては実際の運用が開始されていないこの時点で、すでに改正されるに至った背景は何か。EUのサステイナビリティ目標が後退することを示すのか、あるいは米国のトランプ政権に代表されるような環境政策に対する反発や大きな揺り戻しがあるのか。本ニュースレターでは、こうした疑問に答えると共に、オムニバス法案パッケージの概要と日本企業への影響の見込みを解説します。 (1) EUのサステイナブルファイナンス行動計画と各法律の成立の背景 遡ること2018年、欧州委員会は「サステイナブルファイナンス行動計画」を通じて、資本市場のキャピタルの流れを持続可能な投資を促進する方向に誘導すること、気候変動リスクや環境リスクを金融システムに統合し金融の安定性を確保すること、そして透明性と長期的視点を市場活動に組み込むことを目指しました。この行動計画は2019年にフォン・デア・ライエン委員長の下で発足した欧州委員会に引き継がれ、2050年までに気候中立 (カーボンニュートラル) を実現させることなどを政策目標とした「欧州グリーンディール」の下においても、目標実現に必要な金融システムの改革や、資本を再生可能エネルギー・エネルギー効率化への投資に誘導させるための法的な枠組みが構築されました。 具体的には、EUタクソノミー規則により「持続可能な経済活動」とは何かを定義するための統一基準を整え、欧州の金融機関に対してはサステイナブルファイナンス開示規則(SFDR)[5]を通じて、保有ポートフォリオの持続可能性に関する情報開示を義務付けました。 並行して、EU域内で経済活動を行う企業に対しては、EUタクソノミー規則下で自社の経済活動のうちサステイナビリティ基準に沿う割合の開示を、企業サステイナビリティ報告指令(CSRD)にて広範な範囲における非財務情報の開示を義務付けることで、投資家の判断に共される情報を標準化し、透明性を高めました。従来、サステイナビリティやESG (環境、社会、ガバナンス)報告書に関する国際的なガイドラインはありましたが、いずれも企業の自主的な取組みであったことに対し、EUでは欧州サステイナビリティ報告基準(ESRS)[6]に基づく非財務情報の開示が法的に義務付けられることになりました。また報告内容の正確性を担保するため、ESRSに基づき開示される非財務情報の第三者保証が義務付けられました。まさに非財務情報が財務情報と同格の位置づけとなったのです。 これにより、金融機関としては、気候変動や社会的課題が各企業の長期的な業績に及ぼすリスクと同時に、企業が地球環境や地域社会等に与える正負の影響を同じ指標でベンチマークすることが可能となり、投融資判断に役立てることができます。そして金融機関は自らのポートフォリオの持続可能性に関する情報をSFDRに基づき開示する、という循環が成立しました。 また非財務情報の開示義務の対象には、EU域内の金融市場で上場する企業だけではなく、EU域内で一定規模以上の経済活動を行う日本企業の子会社・支店や、その親会社である日本企業本社グループも含まれることに留意が必要です。そのため、日本企業にとっては、EU地域報告書の新たな発行や、グループ統合報告書のアップグレードに大きな労力が必要であると見込まれています。 (2) オムニバス法案パッケージの背景 このようにEUでは金融政策の一環として、持続可能性を重視した政策を推進してきましたが、欧州委員会が法律の網羅性と正確性を担保しようとすればするほど、つまり法案を作りこめば作りこむほどに、内容は複雑化・高度化し、企業にとっては対応するために必要な事務負担が増加する傾向が生じていました。例えば、ESRSで報告対象となるデータポイントは定量・定性情報を合わせて約1,200もあり、コンサルタントの試算によれば、そのうち中堅規模の企業が報告書に含めるべきデータポイントは平均で500を超えると見込まれます。多くの企業ではこれら非財務情報は社内の広範な部門、部署、子会社等でばらばらに管理されており、中には現在まったく収集・管理されていない情報もあり得ます。これら情報の収集・分析、ESRSに適合するダブル・マテリアリティ・アセスメントの実施、社内ガバナンス体制の構築、ITツールの導入、報告書への取りまとめ等には一般的な企業で2年以上かかると想定され、特に中小企業(SMEs)にとって過剰な負担であり、競争力を損なう可能性が指摘されていました。 さらに、CSRDの双子法律ともいえるCSDDDでは、サプライチェーン上におけるデューデリジェンスの実施義務を大企業に負わせていますが、結局はサプライチェーンに位置する中小企業に情報収集負担や対応コストが転嫁される負の波及影響が生じるのではないかと、長らく懸念されていました。 同時期に、欧州では2020年のパンデミック、2022年のロシアによるウクライナ侵攻とそれに続くエネルギー価格の高騰、近年の地政学的な緊張の高まりといった外部要因が、欧州企業の競争環境をさらに厳しくしており、競争力強化が急務と見なされるようになりました。2024年6月の欧州議会選挙やそれに先立つ主要加盟国の国政選挙では、産業競争力の維持強化が政策争点の一つとなる一方で「緑の党」が大幅に議席を減らすなど、世論全体が明らかに政策の優先順位の変更を求めていることを示したことも、欧州委員長として同時期に再選されたフォン・デア・ライエン氏が政策を見直す後押しになったと考えられます。 そこでフォン・デア・ライエン氏と加盟国首脳は、イタリアの元首相ドラギ氏に、欧州の競争力を高めるための政策的な方向性を示す報告書の作成を依頼しました。2024年9月に公表された通称「ドラギ・レポート」では、複雑で過剰な規制が欧州の競争力を阻害しているとの指摘がなされ、続いて11月にEU加盟国の首脳は「ブダペスト宣言」の中で具体的に“規制の簡素化革命”を欧州委員会に要請しました。欧州委員会はその回答として今年1月に発表した「Competitiveness Compass」において、規制簡素化を優先課題とすることを対外的に示し、企業に対する負担を25%、中小企業に対しては35%削減させることが、今政権のミッションとして明示されました。オムニバス法案パッケージは、このような経緯を経て公表された、複数の具体的な法律改正案のパッケージなのです。 (3) オムニバス法案パッケージのポイント オムニバス法案パッケージに含まれる主な改正案は、以下のとおりです: CSRDの改正 · 報告対象企業の縮小: 持続可能性報告の対象を従業員数1,000人(現法令では500人)かつ売上高5千万ユーロを超える大企業に限定。上場中小企業は報告義務から除外。報告義務の対象企業数が約80%削減されると見込まれます。 · 中小企業への影響軽減: バリューチェーンにおける情報収集の制限を設け、報告対象外の企業に対して過剰な情報要求を行わないよう規定。 · 任意報告基準の導入: 報告義務のない企業が利用できる簡易な任意報告基準を導入。 · セクター別報告基準の廃止: セクター(業界)別の報告基準を廃止し、報告要件の複雑化を防止。 · 保証要件の簡素化: 現行法で予定されていた限定保証(limited assurance)から合理的保証(reasonable assurance)への移行を廃止し、保証コストの増加を防止。 · 適用開始日の延期: 非上場企業(日本企業のEU域内子会社・支店を含む)に対する義務付けを2026年1月から2028年1月(2027会計年度データ)に後ろ倒し。 · 報告基準の改訂: ESRSが定める報告項目のうち自社への関連性が低い項目の情報開示をスリム化、定量的データを優先し強制的な情報開示項目と自主的なものを明確化することで企業の負担を軽減しつつ、国際基準にそろえる。なおブリュッセルでの非公式情報では、欧州委員会がESRSを制定する欧州機関であるEFRAGに対し、報告項目を3割程度減少させるESRS改定案を8月末までにまとめるよう求めているようです。 期待される効果これらの変更により、報告義務が免除される日本企業が増えるでしょう。また企業の報告負担が軽減され、非財務情報の収集・報告にかかるコストがある程度低減することが期待されます。 CSDDDの改正 · デューデリジェンス範囲の縮小: 企業のデューデリジェンス義務対象を直接的なビジネスパートナーに限定し、間接的なパートナーに対する義務を、情報がある場合に限定。 · デューデリジェンス頻度の削減: 定期的なモニタリングの頻度を1年から5年に延長。 […]
